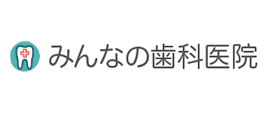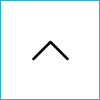細菌の感染によって歯ぐきや歯を支える骨が溶けて、歯の周りの組織が炎症する疾患である「歯周病」は、感染症であるとともに生活習慣が発症のきっかけになることから生活習慣病ともいわれます。
加齢とともに歯周病の有病率が高くなり、30代以上では3人に2人は歯周組織に所見も見られます。そこで今回は歯周病を引き起こす3つのリスクについて解説します。
歯周病は歯周病は口内だけでなく、全身の健康に影響する
歯周病の初期は自覚症状が乏しく、気づかないうちに進行することが多く、進行すると歯ぐきが腫れたり、膿が出たり、歯がグラグラしたりするなど症状が現れます。
日本人が歯を失う原因は「歯周病」と「虫歯」が二大原因となっていますが、40代後半からはムシ歯より歯周病のほうが割合が高くなってきます。
また、炎症によって出てくる毒性物質が歯肉の血管から全身に入り込んでしまうと、糖尿病や脳梗塞など全身の病気を引き起こしたり悪化させる原因となります。
歯周病の原因は「プラーク(歯垢)」と呼ばれる生きた細菌のかたまりです。プラークは抗菌薬が効きにくい構造で、産生する毒素が歯ぐきの腫れや出血、膿の排出や歯の周りの骨を溶かす原因となります。
感染の原因となるプラークを取り除く歯みがきや、食生活などの生活習慣を見直して、全身の病気にもつながるおそれのある歯周病を予防しましょう。
歯周病を引き起こす3つのリスク
ただ丁寧な歯磨きを心がけていても、普段気にもとめないような何気ない毎日の生活習慣や癖が、歯周病のリスクを高めている可能性があります。そして歯周病を引き起こしやすいリスク要因が重複すると、歯周病発症の危険性が高まります。
では、どのようなリスクがあるのでしょうか。歯周病を引き起こすリスクは大きく3つになります。
1:口腔内の要因
歯垢・歯並び・歯みがき・嚙み合わせ・歯ぎしり・食いしばり・口呼吸など
2:環境の要因
ストレス・喫煙・飲酒・食生活・不規則な生活など
3:宿主の要因
年齢・人種・持病・遺伝・肥満・免疫力の低下など
効果的に歯周病ケアするには、やはり基本は正しく歯磨きをすることに限ります。しかし、自己流の磨き方ではきちんと磨けていないことも多いもの。磨き残しがあると歯垢が残ったままになり、歯周病菌の温床となるので正しい歯磨きを覚えましょう。
磨き方のコツ
歯ブラシを歯に強く当てる必要はなく、歯と歯ぐきの間に届くように気をつけながら、細かく動かして歯垢を落とします。歯ブラシの届きにくい部分の歯垢をしっかり落とすためにデンタルフロスや歯間ブラシなどを併用するとよいでしょう。
歯ブラシの選び方
すみずみまで毛先が当たるようヘッドが小さめのものを選びましょう。また、毛先は歯垢を落としやすいようにある程度の固さがあるものを選びましょう。
相模原古淵のみんなの歯科医院で、健康な口腔環境を目指しましょう。
「自分の生活の中にリスクが潜んでいるかもしれない」と意識することが、歯周病対策への第一歩となります。そして、そのリスクを1つずつ減らしていくことが、歯周病予防につながっていきます。
相模原古淵の「みんなの歯科医院」では患者様の口腔状態に合わせた適切なケアはもちろん、皆様の健康な口腔環境づくりをサポートするため、歯周病治療から矯正治療、訪問診療までをトータルに対応しています。
また、予防歯科に力を入れるほか、無料カウンセリングも実施しておりますので、どんなお悩みもまずはお気軽にご相談ください。