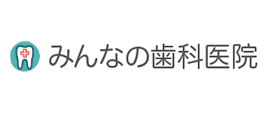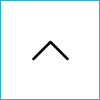相模原・古淵の矯正歯科が解説。歯ぎしりが引き起こす5つの悪影響と改善方法

睡眠中に無意識に歯を擦り合わせてしまう「歯ぎしり」。寝ている間に起きているため、自分ではなかなか気づきにくいものです。しかし、歯はもちろん、顎や全身にもさまざまな悪影響を与える可能性があります。今回は、歯ぎしりが引き起こす代表的な悪影響と、その改善方法について紹介します。
目次
歯ぎしりが引き起こす「5つの悪影響」と検診の必要性
歯ぎしりにはストレスや噛み合わせといった、さまざまな原因があるとされています。放置しておくと歯だけでなく顎や全身にもダメージが及ぶおそれがあるため、正しい知識を身につけて、お口の状態のチェックやケアを怠らないようにしましょう。
また、特に歯ぎしりの大きな原因とされているストレスを甘く見てはいけません。ストレスによって歯ぎしりを引き起こし、睡眠の質が低下することでまたストレスが溜まるという悪循環に陥ってしまいます。
大切な歯と身体を守るため、まずは自分が歯ぎしりをしていないか、検診でチェックしてもらうことが重要です。
歯ぎしりが引き起こす5つの悪影響とは
寝ている間の歯ぎしりは、歯や身体にどのような影響を及ぼすのでしょうか。 主な症状は以下の5つです。
歯がすり減る
歯ぎしりをしている間、歯には自身の体重の3倍ほどの力がかかっているといわれています。毎日のように歯ぎしりが長期間続くことで、徐々に歯がすり減っていき、噛み合わせの悪化にもつながります。それによって食事の際に上手く咀嚼できなくなるおそれもあるのです。
知覚過敏を引き起こす
歯ぎしりによって歯が削れていくことで、表面のエナメル質が薄くなります。歯のエナメル質の厚みは個人差はありますが、一般的には約2〜3ミリ程度です。これが薄くなることでその下にある象牙質と呼ばれる部分に刺激が伝わりやすくなり、歯がしみる知覚過敏となってしまいます。
顎関節症の要因に
顎関節症とは、顎の関節に痛みが起きたり、口を開け閉めすることが難しくなる病気です。日本人は後頭部が短く、顎関節症になりやすい骨格のため、患者数も多いとされています。歯ぎしりをすると、顎の関節を傷めやすくなり、顎関節症を引き起こすリスクが高まります。
歯周病の悪化
歯周病は歯周組織を破壊して歯をグラグラと不安定にさせる病気で、悪化すると最終的には歯が抜け落ちてしまいます。歯ぎしりをすることで歯に強い力が加わるため、歯周組織の破壊を早める恐れがあります。
睡眠の質の低下 睡眠障害
浅い眠りや睡眠時無呼吸症候群などが歯ぎしりを誘発する可能性があります。 睡眠中にギリギリと歯ぎしりをしてしまうことで、目が覚めてしまうことがあります。睡眠の質が下がることで免疫機能の低下にもつながり、感染症リスクや持病の悪化など、さまざまな健康被害の可能性が高まるのです。
相模原古淵のみんなの歯科医院で、歯ぎしりを改善しましょう
歯ぎしりを改善するには、睡眠時に「ナイトガード」と呼ばれるマウスピースを装着して、歯のダメージを防ぐのが有効です。
また、ストレスは歯ぎしりの最大の原因といわれているので、リラックスできる時間を持つなど、ストレス解消を心がけましょう。相模原古淵の「みんなの歯科医院」では患者様の口腔状態に合わせた適切なケアはもちろん、皆様の健康な口腔環境づくりをサポートするため、歯周病治療から矯正治療、訪問診療までをトータルに対応しています。
また、予防歯科に力を入れるほか、無料カウンセリングも実施しておりますので、どんなお悩みもまずはお気軽にご相談ください。
診療のご予約・無料相談
カテゴリー:みんなの歯科医院について